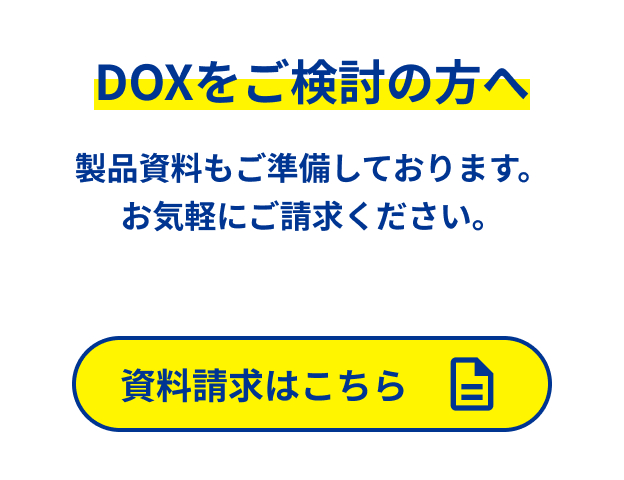培地学シリーズ8
2015.11.15
―ウエルシュ菌選択培地
はじめに
ウェルシュ菌は1882年William.H.Welchにより、ガス壊疽患者からはじめて分離された。1900年にこの報告者のWelchの名前にちなんで“Bacterium welchii”と命名された。その後1937年にClostridium perfringensに学名が変更された。しかし、わが国では、”ウェルシュ菌“という和名が一般に使われている。
ウェルシュ菌は、ヒト、動物の腸管内、土壌、下水などに広く分布し、食品汚染の機会が多い。加えて本菌は耐熱性の強大な芽胞を形成するので、通常の調理程度の加熱では生き残り、食品を常温で保存中に芽胞が発芽、増殖して人に食中毒を発生させる。わが国で発生するウェルシュ菌食中毒は、患者数では全細菌性食中毒の10%近くを占めている。この食中毒はしばしば学校給食や仕出し屋などで大量に作られる弁当や料理で発生するため、大規模食中毒になるケースが多い。
日本における食品からウエルシュ菌の検出用の選択分離培地としてはカナマイシン含有卵黄CW寒天培地、Triptose sulfite cycloserine寒天培地及びハンドフォード改良寒天培地が食品衛生検査指針で推奨されている。今回は日本で最もよく良く利用されているカナマイシン含有卵黄加CW寒天培地について紹介する。
カナマイシン加卵黄CW寒天培地(Clostridium Welchii agar with kanamicin and Egg yolk)

1.原理
CW寒天培地はレシチナーゼ、リパーゼの産生によりウエルシュ菌の分離、推定同定用として、1947年にMcClungとToabeらにより考案された卵黄寒天培地を基礎とする変法培地である。
基礎培地はカゼインペプトン、プロテアーゼペプトンに心臓筋肉エキスが加えられた栄養価の高い組成である。心臓エキスはウエルシュ菌の発育と卵黄反応活性促進のために添加されている。
選択剤として200mg/Lのカナマイシンが含有されている。このためクロストリジュウム属以外のほとんどの細菌の発育を抑制することができる。
鑑別剤として乳糖・フェノール赤と卵黄液が含まれている。従って、乳糖分解菌ではコロニー周囲の黄変、非分解菌は赤変する。同時にコロニー周囲の白濁(ハロー)の有無により、レシチナーゼ活性能が、、真珠様光沢のコロニー形成の有無により、リパーゼ活性が鑑別できる。
本培地でウエルシュ菌は
①コロニーの黄変(乳糖分解)
②コロニー周囲白濁(レシチナーゼ反応陽性)
③真珠様光沢のコロニー(リパーゼ反応陽性)
の性状を示す。
2.組成(精製水1000mlに対して)
| 心臓筋肉エキス | 5g |
| カゼイン膵消化ペプトン | 10g |
| プロテオーゼペプトン | 10g |
| 塩化ナトリウム | 5g |
| 乳糖 | 10g |
| フェノール赤 | 50mg |
| 寒天 | 15g |
| 硫酸カナマイシン | 200mg |
| 卵黄液(50%) | 100ml |
pH 7.4±0.2
3.培地成分の役割
心臓筋肉エキス(心筋エキス)
心臓筋肉エキスは炭素・窒素源としてよりも,ビタミン・核酸・アミノ酸・有機酸・ミネラル等が豊富に含まれるためにウエルシュ菌の生育促進物質と卵黄反応の活性促進の目的で用いられている。心臓筋肉エキスは、心臓筋肉を水で浸出したものを(加熱して)濃縮したものである.通常0.05–0.1%程度の濃度で使用される。
カゼインペプトン・プロテオーゼペプトン(獣肉ペプトン)
細菌が発育するために必須の栄養素は①窒素源②炭素源である。細菌は蛋白分解力をもたない為に、蛋白質をポリペプチドやペプチドの型まで消化または分解しないと栄養素として利用できない。(蛋白を消化または分解した物質をペプトンと言う)培地に一般的に使用されるペプトンとしてはカゼインペプトン・大豆ペプトン・獣肉ペプトン、心筋ペプトン・ゼラチンペプトンである。各ペプトンは培地の組成に合せて選択される。本培地はカゼインペプトン(膵臓のパンクレアチン消化)とプロテオーゼペプトン(獣肉ペプシン消化)の2種類のペプトンが使用されている。カゼインペプトンは経済的に優れ、トリプトファンに富む.含硫アミノ酸が少ない。プロテオーゼペプトン(獣肉ペプトン)はトリプトファンに乏しい.含硫アミノ酸が多い.ビタミンや発育因子が多いなどの特徴がある。
塩化ナトリウム
細胞膜の浸透圧の維持のために用いられている。
乳糖
乳糖(炭水化物)は①エネルギー獲得のための炭素源として②炭水化物の分解による菌種の鑑別のために含まれている。乳糖分解菌と非分解菌を区別するために含まれている。
フェノール赤
フェノール赤はpHの変化によって変色するpH指示薬である。変色域はpH6.8以下黄色、pH8.4以上は赤色です。マンニット分解菌は黄色のコロニーを、非分解菌は赤色コロニーを形成する。
マンニットの分解により酸が産生されて培地pHは酸性になるので黄変し、マンニット非分解の場合は酸の産生がないのでペプトンの分解によるアンモニアの産生のみにより培地のpHはアルカリ性になるため赤変する。
寒天
寒天は培地の固形化剤である。原料は海藻であるテングサ、オゴノリである。細菌検査培地としてはオゴノリが原料として使用されている。(安価であるから)
寒天の主成分はアガロースで糖が直鎖状につながっており、細菌には分解されにくい構造になっている。寒天の内部に水分子を内包しやすく、多量の水を吸収してスポンジ状の構造を形成する。水分を蓄えることができ、栄養分をその中に保持しておける。そのため、微生物の培地に適する。
寒天を加熱していくと解ける温度を融点、また解けた寒天が固まる温度を凝固点と言うが、寒天は融点が85~93℃、凝固点が33~45℃である。これも寒天に混ぜる成分により変動する。良い培地か否かは寒天の品質が重要である。寒天の品質とは透明度、ゼリー強度、粘度、保水力が優れていることである。
卵黄液
ウエルシュ菌の推定同定のための鑑別剤として用いられている。
卵黄液中にはレシチン(リン脂質)とアシールトリグリセリッド(脂質)成分が含まれ、この2つの成分をウエルシュ菌は分解することができるが、他のクロストリジュム属菌の多くは分解することができないため、ウエルシュ菌の鑑別剤として利用されている。レシチンが分解されるとコロニーの周囲はレシチンの結晶化により白濁する(ハロー現象)。さらにアシールグルセリッドの分解により表面が真珠のような光沢のあるコロニーを形成する。この反応をリポビテリンリパーゼ(lipovitellin lipase)反応と言う。
カナマイシン
クロストリジュウム属の細菌の選択剤として用いられている。カナマイシンはグラム陰性菌からグラム陽性菌までの広域スペクトルを有するアミノ配当体系抗生物質である。しかしクロストリジュム属の細菌に対しては抗菌効果がない。そのために本培地ではクロストリジュウム属菌以外の多くの細菌は発育できない。
4.使用法<定量培養> #定性法で陽性の場合は実施する。
① 食品の10%乳剤を10 倍段階希釈する。
② 各希釈段階の 0.1 ml をカナマイシン加卵黄CW寒天培地上に滴下し、コンラージ棒で広げる。
③ 37℃で24時間・嫌気培養する。
④ 乳糖分解(+)、卵黄反応(+)集落の数をカウントし、1g 当たりの菌数を算出する。
5.培地の限界
1.ウエルシュ菌以外の菌種が発育する。
Clostridium spp. 、Bacillus cereus 、Pseudomonas aeruginosa 、Enterococcus spp.などのウエルシュ菌以外の菌種が発育する。
2.ウエルシュ菌以外の菌種でレシチナーゼ反応陽性を示す。(コロニー周囲の白濁帯)
Closiridium属の一部の菌種(Clostridium novyi)やBacillus cereusはコロニー周囲の混濁(ハロー)が認められる。(卵黄反応陽性)
3.レシチナーゼ反応陰性のウエルシュ菌がある。
国内の食中毒発生例でカナマイシン加卵黄CW寒天培地で卵黄反応陰性の分離事例が報告されている。
4.乳糖遅分解のウエルシュ菌がある。
ウエルシュ菌は乳糖分解するため、本来はコロニー周囲が黄変する。、乳糖非分解又は遅分解のウエルシュ菌はコロニー周囲が赤変する場合がある。
5.食品中のウエルシュ菌は加熱、乾燥、凍結や製造工程により細胞膜・細胞壁がダメージを受けると(損傷菌)発育が抑制または阻止される。(損傷菌対策剤不含のため)
食品中に存在または表面に付着するウエルシュ菌の損傷菌は発育不良です。食品中の細菌は加熱、乾燥、凍結や製造工程により細胞膜・細胞壁がダメージを受けると(損傷菌)発育が抑制または阻止される。特に培地に含まれている抗生物質(カナマイシン)には損傷菌に対して影響を受けやすいために発育が不良になる。
6.カナマイシンに感受性を示すウエルシュ菌は本培地には発育できない。
カナマイシン感受性のウエルシュ菌による食中毒の事例報告では、分離株のカナマイシンのMICを測定したところ、培地含有のカナマイシン200μg/mlよりも低い125μg/mlであり、カナマイシン加卵黄CW寒天培地では発育しなかった。<文献>
(選択剤として使用されているカナマイシンの限界)
6.参考文献;
McClung and Toabe,1947,J.Bacteriol.53:139
G.L.Chrisope et al 1976, App.and environmental microbial. P789-786
Gubash SM et al 1991, Res.Microbiol. 14(1):87-93
Chambliss,L.S et al 2006,J.Food Prot..,69,2058-2065
Barak,E. Ricca and S. M. Cutting: 2005.Mol. Microbiol.55 ,33 0-338
友近健一:2002.防菌防黴学誌、30:85-90
坂崎利一:新 細菌培地学講座 近代出版 1988
清水茂雄:2009.北大水産彙報59(2)、37-42
東京都健康安全研究センター 微生物部食品微生物研究科 ホームページ
http://idsc.nih.go.jp/iasr/29/342/dj3432.html
門間千枝:2008 日本食品微生物学会雑誌、25,76-82
森地敏樹:1989 防菌防黴学雑誌、17,541-550